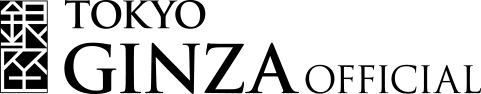
銀ぶら百年
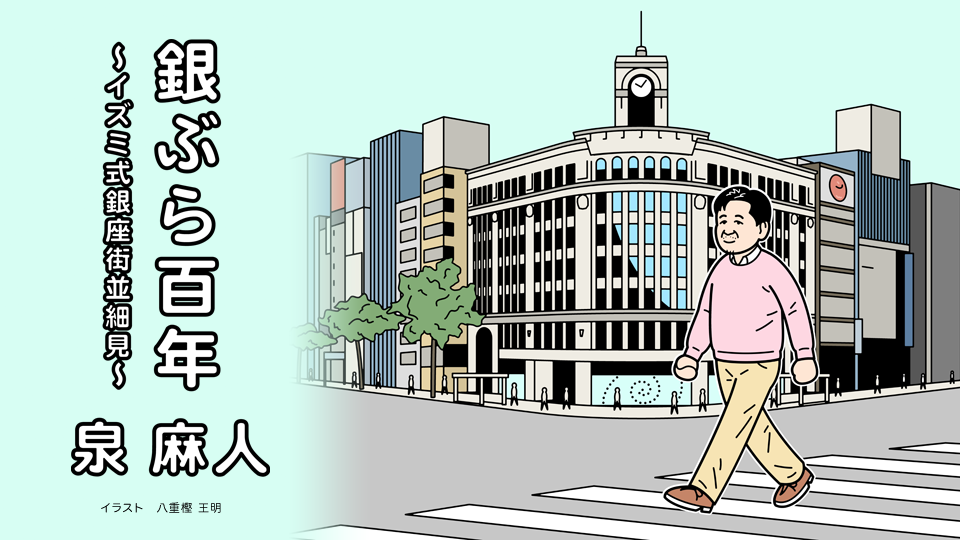
Ginza×銀ぶら百年 Vol.20
銀ぶら百年 ~イズミ式銀座街並細見~
東銀座のインド 「ナイル」をつくった人々
2019.03.25
三原橋の交差点は新橋寄りの角に足袋の大野屋の古めかしい建物が残っているけれど、昭和通りを京橋側に行った2、3軒目にインド料理のナイルレストランがいまも小さな2階建ての建物でがんばっている。

夕暮れにはカラフルなネオンが灯る
僕がこの通称「ナイル」に初めて行ったのは、おそらく1980年代の初めごろ。マガジンハウス(まだ「平凡出版」の名義だったかもしれない)の「POPEYE」誌なんかで短い原稿を書き始めたころ、編集者やライター仲間に連れられて行った。名物のムルギーランチを注文したときにインド人の店員がセカすように指示する「混じぇて食べて~」のフレーズや食べ切れずに残してしまったときに「なぜ残す、なぜ食べない?」としつこく問われる……ああいう口調のマネをするのがハヤッたこともあった。
実はもう10年あまりごぶさたしてしまっているのだが、このたび2代目にあたるG・M・ナイル氏じきじきにお話をうかがう機会を得た。平日の夕刻5時、指定された時間に訪ねると、昼夜間の休みのないこの店は、早くも1階のテーブルがおおかた埋まっている。奥の厨房脇のイスに座って、店の客の様子に目を配っているのが、80年代のころから「混じぇて食べて」と指示して回っていたラジャンというベテラン店員だろう。
2階に通されて待っていると、やがてG・M氏がやってきた。
「すんませんねぇ、遅れちゃって。国立劇場で清元の稽古やってましてね」
芸能界でも活躍するG・M氏、とりわけ歌舞伎の清元には古くから通じている。稽古といっても氏が教える側なのだ。流ちょうな早口で語るG・M氏のお話と、氏から許可をもらった自叙伝的な本『銀座ナイルレストラン物語』(水野仁輔・著)を参考にしながら、書き進めていこうと思う。
まず、この店が誕生したのは戦後の1949年(昭和24年)というから、裏を流れる三十間堀川が埋め立てられた(空襲によってあふれたガレキの処理が目的だった)ころだろう。戦中の44年生まれのG・M氏が5歳のころのことになるが、周辺の景色は記憶に残っているという。
「銀座っていってもこの辺はひどかったよ。とくに夜なんかはGIとパンパン、晴海通りにテキヤの露店がずらーっと並んでいて、とにかくガラが悪いのがいっぱいいてね……」
GHQの施設は和光や松屋の建物に入っていたPXなど銀座の中心街にもあったが、この辺から近い現在の国立がん研究センターの一帯には米軍の専用病院や大きなランドリー工場があったというから、GIがウロウロしていたのは土地柄ともいえる。
さて、店を立ち上げたG・M氏の父、A・M・ナイル氏はインドのアラビア海側の南西端、ケララ州の出身で、若いころから反英主義の独立運動に情熱を燃やしていた。そして、昭和初めの1928年、来日して京大(京都帝国大学)に留学する。京大留学に関しては、A・M氏の父、G・M氏の祖父にあたる人が日本びいきだったからだという。その理由がおもしろい。日露戦争で乃木大将がステッセル将軍を倒し、日本海海戦で東郷元帥がバルチック艦隊に勝利し、つまりアジアで初めて白人に勝った日本人はすばらしい……といった根拠なのだった。
A・M氏は京大卒業後、満州で大学の教員などを務めて、日本で終戦を迎える。47年にインドも独立を果たして、1つの目的を失う。「とりあえず、家族を食わせていかなくちゃ」というので始めたのがインド料理店だった。
と、こういったお話を聞くと、A・M氏は料理が得意だったと思うのが普通だろうが、氏はほとんど食には無頓着で、厨房を仕切ったのは満州で結婚した日本人の妻・由久子さんのほうだった。なんでも、満州時代に近所に住んでいたインド人家族から由久子夫人がカレーのつくり方などを教わったのが発端らしい。
開店当初の占領下の時代は、先述したGHQのGI連中が主客だったという。反英主義者だったA・M氏としては複雑な心境だったかもしれない。
とはいえ、祖国インドを思う愛国心が薄れることはなく〈日印親善は台所から〉というメッセージが長らく各テーブルに掲示されて、これが店内のシンボルにもなっていた。
そう、看板メニューのムルギーランチは、チキンカレーの1種といっていいものだが、鶏肉は比較的かたい肉質の地鶏(骨付き)が使われて、同じプレートにライスのほか、湯がいたキャベツとジャガイモが盛りつけられている。これを「混じぇて食べて」と最初にいい出したのはA・M氏だという。料理に無頓着とはいえ、なにかひらめくものがあったのだろう。
実はもう10年あまりごぶさたしてしまっているのだが、このたび2代目にあたるG・M・ナイル氏じきじきにお話をうかがう機会を得た。平日の夕刻5時、指定された時間に訪ねると、昼夜間の休みのないこの店は、早くも1階のテーブルがおおかた埋まっている。奥の厨房脇のイスに座って、店の客の様子に目を配っているのが、80年代のころから「混じぇて食べて」と指示して回っていたラジャンというベテラン店員だろう。
2階に通されて待っていると、やがてG・M氏がやってきた。
「すんませんねぇ、遅れちゃって。国立劇場で清元の稽古やってましてね」
芸能界でも活躍するG・M氏、とりわけ歌舞伎の清元には古くから通じている。稽古といっても氏が教える側なのだ。流ちょうな早口で語るG・M氏のお話と、氏から許可をもらった自叙伝的な本『銀座ナイルレストラン物語』(水野仁輔・著)を参考にしながら、書き進めていこうと思う。
まず、この店が誕生したのは戦後の1949年(昭和24年)というから、裏を流れる三十間堀川が埋め立てられた(空襲によってあふれたガレキの処理が目的だった)ころだろう。戦中の44年生まれのG・M氏が5歳のころのことになるが、周辺の景色は記憶に残っているという。
「銀座っていってもこの辺はひどかったよ。とくに夜なんかはGIとパンパン、晴海通りにテキヤの露店がずらーっと並んでいて、とにかくガラが悪いのがいっぱいいてね……」
GHQの施設は和光や松屋の建物に入っていたPXなど銀座の中心街にもあったが、この辺から近い現在の国立がん研究センターの一帯には米軍の専用病院や大きなランドリー工場があったというから、GIがウロウロしていたのは土地柄ともいえる。
さて、店を立ち上げたG・M氏の父、A・M・ナイル氏はインドのアラビア海側の南西端、ケララ州の出身で、若いころから反英主義の独立運動に情熱を燃やしていた。そして、昭和初めの1928年、来日して京大(京都帝国大学)に留学する。京大留学に関しては、A・M氏の父、G・M氏の祖父にあたる人が日本びいきだったからだという。その理由がおもしろい。日露戦争で乃木大将がステッセル将軍を倒し、日本海海戦で東郷元帥がバルチック艦隊に勝利し、つまりアジアで初めて白人に勝った日本人はすばらしい……といった根拠なのだった。
A・M氏は京大卒業後、満州で大学の教員などを務めて、日本で終戦を迎える。47年にインドも独立を果たして、1つの目的を失う。「とりあえず、家族を食わせていかなくちゃ」というので始めたのがインド料理店だった。
と、こういったお話を聞くと、A・M氏は料理が得意だったと思うのが普通だろうが、氏はほとんど食には無頓着で、厨房を仕切ったのは満州で結婚した日本人の妻・由久子さんのほうだった。なんでも、満州時代に近所に住んでいたインド人家族から由久子夫人がカレーのつくり方などを教わったのが発端らしい。
開店当初の占領下の時代は、先述したGHQのGI連中が主客だったという。反英主義者だったA・M氏としては複雑な心境だったかもしれない。
とはいえ、祖国インドを思う愛国心が薄れることはなく〈日印親善は台所から〉というメッセージが長らく各テーブルに掲示されて、これが店内のシンボルにもなっていた。
そう、看板メニューのムルギーランチは、チキンカレーの1種といっていいものだが、鶏肉は比較的かたい肉質の地鶏(骨付き)が使われて、同じプレートにライスのほか、湯がいたキャベツとジャガイモが盛りつけられている。これを「混じぇて食べて」と最初にいい出したのはA・M氏だという。料理に無頓着とはいえ、なにかひらめくものがあったのだろう。

インドのビール、その名もマハラジャ。
ところで、ナイル一家の住まいは店のある銀座近辺ではなく、文京区の現・本駒込あたりにあった。そして、G・M少年はエリート校東京教育大学附属小学校(現・筑波大学附属)に通学することになる。この家は母・由久子さんが地図に線を引いて、東大と教育大附属小の中間(本駒込は若干北だが)地点を目安に場所決めしたというから、子どもの教育環境が念頭にあったものといえる。京大進学の父といい、それを決めた祖父も学者だったというし、ナイル一族は代々インテリ肌の家系だったのだ。
この親の構想からして、G・M少年は東大進学をめざしたのか……というと、結局東京農業大学に進んだ。
「ボクは料理や食品に興味をもっていたんでね、東大の農学部に行きたいっていったんだけど、するとオヤジが実務を身につけるんだったら農大のほうがいいっていいだしてね」
2代目の夫人・満子さんは、他校ながら農大時代に知り合った人というから、父のチョイスは正しかったのかもしれない。
世田谷の東京農大に入った1年生の年から2代目G・M氏は店の仕事を手伝うようになった。
「おまえももう18になったんだから、っていきなり年の始めの1月から5月までインドに戻っちゃったんだ、オヤジ。そんで、年の前半5ヵ月はボクが店を任されるようになったんですよ」
ライオンの親が子を崖から突き落として成長を待つ……みたいな心理だったのだろうか。しかし、4年間で仕事もおぼえて、卒業後に店を継ぐ意志を伝えたG・M氏に先代A・M氏は当初猛反対した、というのだから、父親の心は揺れていたのだ。
この親の構想からして、G・M少年は東大進学をめざしたのか……というと、結局東京農業大学に進んだ。
「ボクは料理や食品に興味をもっていたんでね、東大の農学部に行きたいっていったんだけど、するとオヤジが実務を身につけるんだったら農大のほうがいいっていいだしてね」
2代目の夫人・満子さんは、他校ながら農大時代に知り合った人というから、父のチョイスは正しかったのかもしれない。
世田谷の東京農大に入った1年生の年から2代目G・M氏は店の仕事を手伝うようになった。
「おまえももう18になったんだから、っていきなり年の始めの1月から5月までインドに戻っちゃったんだ、オヤジ。そんで、年の前半5ヵ月はボクが店を任されるようになったんですよ」
ライオンの親が子を崖から突き落として成長を待つ……みたいな心理だったのだろうか。しかし、4年間で仕事もおぼえて、卒業後に店を継ぐ意志を伝えたG・M氏に先代A・M氏は当初猛反対した、というのだから、父親の心は揺れていたのだ。

特注のシャツはどれもカラフル!
ともかく、店の後継ぎを許された2代目、先代とおおいに異なっていたのは、食についての飽くなき探求心だ。店に入って数年目の70年、大阪万博のインド館のレストランでの修業話が舞いこんだ。このとき、レシピを教えたがらない先輩コックにこっそり身銭(千円、2千円くらい渡したという)を切って、インド料理の基本メニューを徹底的に学んだ。
70年代、80年代と銀座の店は軌道に乗って、観光客も訪れる有名店に成長していく。店のメジャー化には、マスコミの取材にも積極的な2代目のタレント性がおおいに貢献したといえるだろう。そして、G・M氏には清元のような芸能とは別の‶趣味″があった。警察とその活動が大好きなのだ。これはパトカーなどの車両や制服を愛好する、いわゆるマニアではなく、先代の愛国運動と同じく、正義感に根ざしたものなのだろう。
いまからおよそ20年前、97年の5月にナイルレストランは火災に遭(あ)ったが、このときも古くからの親交がある刑事が建物の新築に尽力してくれた。
隣家からの出火がもとで店は柱1本残してほぼ全焼。場所は東銀座の一等地、ハイエナのように土地を狙うコワモテの人々を親友刑事の助力でうまくかわしながら、地上権を買い取って、‶改築″という名目で以前とほぼ同じ高さの2階建の店を復活させた。いま思うと、火災に見舞われなければ、また地上権交渉に失敗していたら、高層のビルに建て替わっていた可能性は高い。そして、焼け残った古い柱が現在もどこかに存在するという。
――どこにあるんですか?
G・M氏に尋ねてみたが、
「さて? あの壁の奥あたりに埋まっているかな……」
回答をはぐらかされた。
そんな話をうかがっているこの2階のスペースで、目につくのは横壁に描かれたインドの風景画。千葉迦陵(かりょう)という画家の手による作品で「クリシュナ神と牛飼い女 ゴーピーたち」という題名がついている。
ガンジス川の田園地帯を舞台にしたこの風景画、よく見ると、センターに描かれた民族衣装の女性は店の名物ムルギーランチの皿を手にしていて、右端にはA・M氏とG・M氏、そして3代目の現社長・善己氏の幼児のころの姿が描写されている。A・M氏がインドの国旗を掲げているのはいいとして、G・M氏が‶警察手帳″を携帯しているのには、思わず笑ってしまった。
70年代、80年代と銀座の店は軌道に乗って、観光客も訪れる有名店に成長していく。店のメジャー化には、マスコミの取材にも積極的な2代目のタレント性がおおいに貢献したといえるだろう。そして、G・M氏には清元のような芸能とは別の‶趣味″があった。警察とその活動が大好きなのだ。これはパトカーなどの車両や制服を愛好する、いわゆるマニアではなく、先代の愛国運動と同じく、正義感に根ざしたものなのだろう。
いまからおよそ20年前、97年の5月にナイルレストランは火災に遭(あ)ったが、このときも古くからの親交がある刑事が建物の新築に尽力してくれた。
隣家からの出火がもとで店は柱1本残してほぼ全焼。場所は東銀座の一等地、ハイエナのように土地を狙うコワモテの人々を親友刑事の助力でうまくかわしながら、地上権を買い取って、‶改築″という名目で以前とほぼ同じ高さの2階建の店を復活させた。いま思うと、火災に見舞われなければ、また地上権交渉に失敗していたら、高層のビルに建て替わっていた可能性は高い。そして、焼け残った古い柱が現在もどこかに存在するという。
――どこにあるんですか?
G・M氏に尋ねてみたが、
「さて? あの壁の奥あたりに埋まっているかな……」
回答をはぐらかされた。
そんな話をうかがっているこの2階のスペースで、目につくのは横壁に描かれたインドの風景画。千葉迦陵(かりょう)という画家の手による作品で「クリシュナ神と牛飼い女 ゴーピーたち」という題名がついている。
ガンジス川の田園地帯を舞台にしたこの風景画、よく見ると、センターに描かれた民族衣装の女性は店の名物ムルギーランチの皿を手にしていて、右端にはA・M氏とG・M氏、そして3代目の現社長・善己氏の幼児のころの姿が描写されている。A・M氏がインドの国旗を掲げているのはいいとして、G・M氏が‶警察手帳″を携帯しているのには、思わず笑ってしまった。

千葉迦陵作品の壁画に描かれたナイルさん一家
「この絵ね、実は未完成なんですよ。ほら、この女性の指なんか完全にできあがってないでしょ。完成を前に作者が亡くなっちゃったんですよ」
まあ、細部を指摘されなければわからないレベルなのだが、この‶未完成″の部分をG・M氏、大切にしているような気がする。
まあ、細部を指摘されなければわからないレベルなのだが、この‶未完成″の部分をG・M氏、大切にしているような気がする。
All List
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.28 憧れの「米倉」で床屋談義
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.27 木挽町の活字屋さん
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.26 西銀座通りの民芸の王様
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.25 銀座復興を願って「はち巻岡田」へ
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.24 三愛のビルを建てた男
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.23 シャツのナカヤの魂を受け継いだジム
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.22 百年目の「銀座通連合会」
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.21 呉服の越後屋、健在
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.20 東銀座のインド 「ナイル」をつくった人々
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.19 聖なる気分で教文館
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.18 ニュースタイルの西銀座デパート
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.17 トラヤ帽子店のパナマ帽
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.16 テイメンと銀座アイビー時代
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.15 ペコちゃんのクリスマス
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.14 夏だ! ビールだ! ライオンだ!
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.13 よし田コロッケそば伝説
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.12 パイプとつやふきんの佐々木
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.11 月光荘とメザシの思い出
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.10 小学校の王様 泰明小探訪
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.09 銀座の煎餅屋ここにあり
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.08 明治44年の銀座広告
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.07 幻の展望ビル・天下堂のナゾ
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.06 サヱグサのシックな歴史を学ぶ
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.05 三笠会館の唐揚げのヒミツ
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.04 1971年夏の山野楽器
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.03 1丁目の銀座アパート
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.02 思い出のオリンピック
- Ginza×銀ぶら百年 Vol.01 歳末の伊東屋詣








